釣り人の間で“ゴールデンタイム”と呼ばれるのが 朝まづめと夕まづめ。
アジングでも特に注目される時間帯で、アジの活性が一気に上がり、普段は口を使わない個体まで積極的に捕食に入る瞬間です。
興味深いのは、釣りをしない人でさえ「朝と夕方は魚が釣れる」と知っているほど有名な現象だということ。これは、魚の行動リズムと環境変化が重なる特殊な時間帯だからこそ起こる現象です。
今回はアジングにおけるまづめの考え方をご紹介します。
そもそも「まづめ(まずめ)」とは?
朝まづめとは日の出前後1時間程度。対照的に夕まづめは日没前後の約1時間のことです。
一般的にまづめは魚の食事時とされており、多くの魚種で釣れる時間帯と言われています。アジも当然その例外ではありません。

ちなみに漢字で「間詰め」なので「まづめ」の方が正しい気がしますが、多くのメディアでは”まずめ”と表記されます。一般的なのは”まずめ”の方でしょう。どちらも間違いとまでは言えないのですが、この記事では”まづめ”と表記させていただきます。
季節によって長さや開始時間が変わります。夏は日の出が早く、朝まづめは午前4時台に訪れることもあれば、冬は日の出が遅いため6時台以降になることもあります。
この薄暗い時間帯が重要になるのは、光量の変化が魚やベイトに大きな影響を与えるためです。

魚には人間のように時計はないですからね。本能的に太陽光によって食事のタイミングが管理されてるのかもしれませんね。
なぜアジが釣れるのか?
アジがまづめ時に釣れやすい理由は、複数の条件が同時に重なっています。いくつかご紹介しましょう。
昼行性と夜行性の境界
魚には昼に活発になる種類(昼行性)と夜に動く種類(夜行性)が存在します。
アジ釣りは夜が盛んですが、実はアジは夜行性ではなく、昼行性の魚です。
なのでアジは基本的には夜にプランクトンを追って活性化しますが、日中もベイトや潮の条件次第で普通に食ってくるわけです。
つまりまづめ時は、夜から食いたい派の群れと、昼間から爆食している群れが加わり、水中に複数の捕食者が同時に存在する状態となります。これが魚全体の“活性の爆発”を引き起こす大きな要因です。
ベイトの移動
プランクトンや小魚は光量に敏感で、朝は浮いていた群れが沈み、夕方には逆に浮上する傾向があります。
それを追うアジの動きも自然と活発化し、捕食連鎖が生まれます。
水中に「ベイトの移動+捕食者の活性上昇」が同時に起こるため、アジングではこの時間帯に釣果が集中するのです。
水温の変化
水温による影響も無視できません。アジの適正水温は16~26℃なので、これによる活性の変化が起きるわけです。
例えば夏は昼間の高水温を避け、比較的涼しい時間帯に活性が上がります。夕まづめはどうしても昼間の影響が残っているため、どちらかと言えば朝まづめの期待値が高くなります。
逆に冬に向かうにつれて全体的な水温が下がるわけですから、朝まづめの反応が徐々に悪くなります。
また、冬はどうしても海水温が低くなる。逆を言えば日中のわずかな水温上昇がかえって最大のチャンスになることがあり、俗にいう“昼まづめ”が発生する可能性があるわけです。
潮の動き
潮汐の変化もアジの捕食行動に大きく関与します。特に朝と夕方は満潮や干潮と重なりやすく、潮が動き出すタイミングに当たりやすいのです。
上げ始めや下げ始めはベイトの動きが活発化し、それを追うアジの捕食スイッチが入る瞬間でもあります。
まづめ狙いのリスクと注意点
アジングにおいてまづめは確かに釣れる時間帯ですが、同時にリスクも存在します。
まずは、釣り人への危険性が高いこと。朝まづめは言うまでもなく睡眠の問題。クッソ眠たい時間帯に動くわけですから、集中力が低下し、思わぬ事故やアタリを逃すなどの釣果に影響する問題も起きやすくなります。朝霧により視界不良に陥る可能性も否定できません。
じゃあ夕まづめはいいのかといえば、昼間との明暗差により、落水リスクが高まります。明るいからと油断していて、夜になったら真っ暗。ヘッドライト忘れて周りが見えなくなりそのままドボンなんてことも考えられます。
さらにまづめによる活性上昇はアジだけの現象ではありません。アジは非捕食者でもあるため、他の魚種の活性が爆上がりした結果、かえってアジが釣れなくなることも考えられます。
そのため、アジングのメインと言われているのは、どちらかというと夜になるわけです。暗い方が見つかりづらいですし、常夜灯効果もあるからですね。

じゃあまづめは釣れないの?

そういうわけではありません。まづめも活性が上がるタイミングであることは間違いないですからね。なので、釣る時間帯はまづめを絡めながら暗い時間帯も含めた時間。短時間なら日の出直前から、日の入直後を狙うといいでしょう。
いずれにせよ釣れる時間帯だからこそ気持ちが高ぶりがちですが、安全装備と冷静な判断は欠かせません。
まづめはクリアカラーを意識しよう

まづめを狙うならどんなワームカラーがいいの?
条件にもよりますが、僕ならアピール力が高い色を試した後に、徐々に透明度をあげます。
まづめは昼間と比べれば光量が少ないですが、夜中に比べればまだまだ明るい時間帯です。
明るいということは、アジもまたワームがよく見えているということです。そのためプランクトンパターンなら透明度が高めのものがハマりやすいです。
ただし、そもそもアジがエサを見つけられなければ捕食するわけがないので、先にチャートなどのアピールカラーを通し、反応を見るわけです。
また絶対ではありませんが、オレンジ系がハマるケースが多いため、カラーローテーションに含めるようにしてます。
ただ例外もあって、30分釣行など短時間で決めたい時は、潮の濁りをみていきなりクリアラメから攻めることも多いですね。
まとめ まづめにこだわりすぎるのも考えもの
いかがでしたか?
アジングにおける朝まづめと夕まづめは、以下のような条件が重なり、釣果が伸びやすい時間帯となります。
・光量変化によるベイトや魚の活性上昇
・昼行性と夜行性の境界が重なる特殊な時間帯
・水温・潮の変化が一気に作用するタイミング
ただし「必ず釣れる」わけではなく、その日の水温や潮を読み、適切な時間を見極めることが重要です。
釣り人の生活環境によっては、まづめを狙いづらいこともありますし、まづめに狙ったけど釣れないなんてよくあることなので、あまり深く考えず「ちょっと確率が上がる程度」と思った方がいいかもしれませんね。
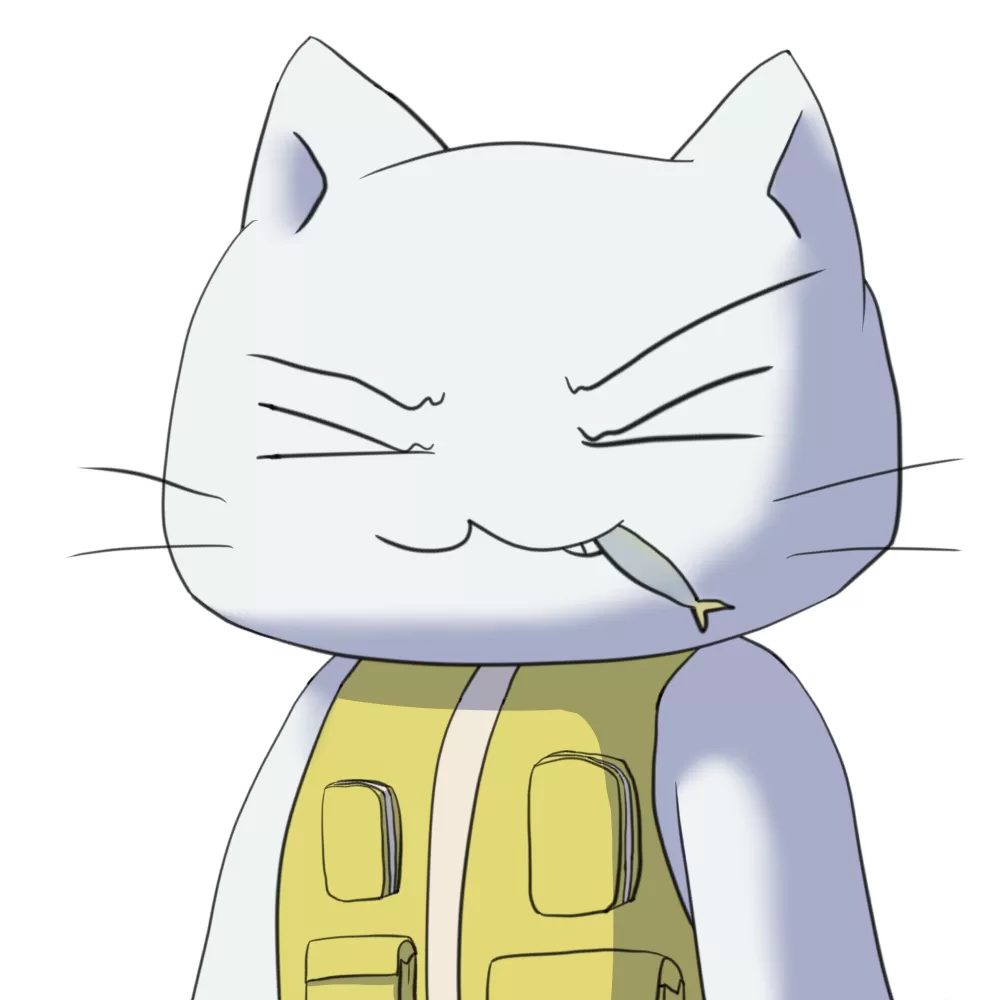
釣りはこのちょっとした確率アップの積み重ねが釣果を分けるとも言えるがな




コメント